前回までは、学びのリズムを「止めない」「重ねる」「今の中に置く」
という話をしてきました。
それは、勉強を“特別な時間”ではなく、“日常の一部”として整えていくという考え方でしたね。
そして今回のテーマは――
「部活を引退してから勉強を始めるのでは遅いのか?」
という、多くの中学生・高校生、そして保護者の方が抱く現実的な問いです。
部活をしている時間は、間違いなく人生の中で特別な時間です。
仲間と共に汗を流し、勝ち負けに悔し涙を流し、
練習が終わる夕暮れの匂いの中に“青春”という言葉の意味を知る。
私は、その時間を否定するつもりはまったくありません。
むしろ、全力で部活に打ち込む子ほど、勉強にも伸びしろがあると思っています。
なぜなら、部活を通して学ぶのは、技術ではなく「続ける力」だからです。
疲れていても行く。うまくいかなくても次を考える。
そうした習慣の中で育つ“粘りと整える力”は、
勉強の世界でもそのまま通用します。
問題は、「引退したあと」です。
多くの子が、部活を終えた瞬間にぽっかりと心に穴が空きます。
それまで毎日、目的を持って動いていた分、
急に“やることがなくなった時間”が増える。
本来はその時間こそが、勉強に向かうチャンスなのですが――
実際には、すぐに切り替えられる子は多くありません。
“部活を引退したから、これからは勉強だ!”
そう決意しても、体も心もすぐには反応しない。
なぜなら、人間は「止まってから動き出す」よりも、
「動きながら方向を変える」ほうがはるかに得意だからです。
だからこそ、私はこう伝えたいのです。
勉強と部活は、切り替えるものではなく、
少しずつ“重ねて”いくものだと。
引退という節目の前から、少しずつ勉強を生活に組み込んでおく。
そうすることで、引退後に“ゼロから”始める必要がなくなります。
一日15分でもいい。
それを“特別な日”ではなく、“いつもの日”に組み込むこと。
勉強はテストのためだけにするものではなく、
歯を磨いたり、お風呂に入ったりするのと同じように、
日常の中に置くものです。
テスト直前だけ机に向かう勉強は、本当の勉強ではありません。
テストが終わったあと、分からなかったことをもう一度できるようにする――
それこそが、正しい意味での“テスト勉強”なのです。
そして、もうひとつ大切なのは、
「部活の中で育った力を、勉強でも使える」と気づくこと。
練習をサボらなかった根気、
試合前に気持ちを整えた集中力、
仲間を支えた責任感。
それらは、机の前に座った瞬間に消えるものではありません。
むしろ、勉強の場に持ち込むことで、
学びの強度がぐっと増していくのです。
「部活で培った集中力」は“勉強の筋肉”に変わり、
「努力の癖」は“理解の継続”に変わる。
子どもがこれまで積み上げてきたものは、
無駄になるどころか、これから本領を発揮する準備を整えています。
私は塾で、よくこう話します。
「勉強は、“始める”ものではなく、
普段の生活の中に“加えて整えていく”ものです。」
勉強の時間を特別につくるのではなく、
いつもの暮らしを少し整えるように、
学びを自然に重ねていけばいいのです。
生活の流れの中に“学ぶ呼吸”を残しておけば、
部活を引退したあとも、流れが途切れない。
それは“切り替え”ではなく、“続きの延長”なのです。
「勉強と部活は違う世界」ではなく、
「努力の方向が違うだけ」。
その感覚をつかんだ子は、どんな変化にも強くなります。
そして、“頑張る”という行為が
「誰かに言われてやること」ではなく、
「自分が決めてやること」に変わっていく。
その瞬間、学びはもう“義務”ではなく“自分の力”になるのです。
次回・第4回 第2パートでは、
「時間の壁――“一気に取り戻す”は成立しない理由」
というテーマでお話しします。
部活を引退したあと、
なぜ“時間ができたのに勉強が進まない”のか。
その構造を、わかりやすく解き明かします。







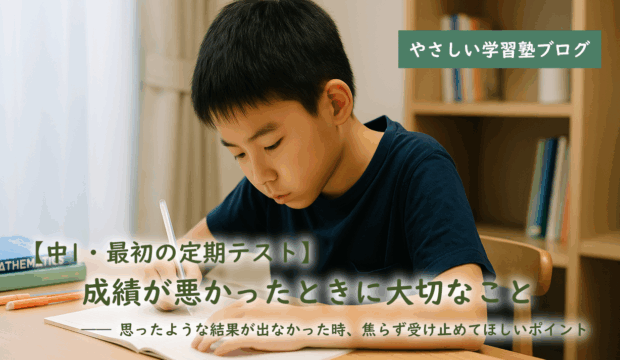
コメント