私が指導で気をつけていること5選
――私は“こういうヤバイ先生にはなりたくない”と思っている――
塾の仕事を長くしていると、いろんな先生と出会います。
実際に会うこともありますし、生徒や保護者からのお話で聞くこともあります。
情熱を持って生徒に向き合う人もいれば、どこか「作業」としてこなしている人もいる。
なかには、正直「この先生、ちょっと危ないな」と思うこともあります。
もちろん、どの塾にも、どの学校にも、良い先生もいればそうでない先生もいます。
だからこそ私は、「自分がそうならないように」と意識して、
日々の指導に向き合っています。
今日はその中から、特に大切にしている5つのことをお話しします。
① 生徒の意見を“聞かない先生”にならない
受験指導では、先生が生徒を導く立場です。
でも、その「導く」が「押しつける」に変わる瞬間があります。
たとえば、志望校を相談したときに
「いや、君はこの地元の国立大でいいんだ」
「その志望校の薬学部は受からないから、こっちの偏差値の低い工学部にしなさい」
――そんな風に言われてしまうことがある。
本人の想いを最後まで聞かずに、先生の“理想の進路”をそのまま当てはめてしまう。
大学の入試レベルを下げるだけならまだしも、学部や学科まで変えてしまう。
それだけは避けたいと思っています。
もちろん、「生徒の希望をすべて通す」のが正しいわけではありません。
時には止める勇気も必要です。
でもまずは、「どうしてその大学を選んだの?」「何を学びたいの?」
と聞くところから始めたい。
塾というのは、お金を頂いて成り立っている場所です。
だからこそ、発言に“権威”が生まれてしまう。
こちらが意図せずとも、「お金を払っている=正しいことを言ってくれる人」という
見方をされやすい。だからこそ、私たちは自覚的でなければいけません。
一方で、学校というのも別の形で“権威”を帯びています。
長く「聖職」と受け止められてきたゆえに、「先生は正しい」「先生が言うなら間違いない」という
盲信が、社会の中で半ば当然のように受け入れられてきました。
その“正しさの幻想”が、時に子どもたちの声を小さくしてしまうことがあります。
学校の先生方の多くは誠実で熱心です。
けれど、制度の中で“正しさ”を守るあまり、個の想いを聞く余裕が奪われることもある。
私たち塾は、その制度の外にいる者として、もう一度「個の声」を拾い上げる役割を担うべきだと感じています。
「先生が正しい」ではなく、「その子の選択が、より良い実りを得られるように」――
それを支えるのが、塾という場所の存在意義だと思っています。
② 綺麗事だけで終わらせない
「君なら大丈夫」「頑張ればなんとかなる」
そんな言葉で安心させることは簡単です。
でも、現実を見ずに綺麗事だけで終わらせるのは、教育ではなく“慰め”です。
受験は、確率と運の世界です。
第1志望に合格する可能性より、合格しない可能性の方が圧倒的に高い。
だから私は、きれいな言葉より、現実的な指摘をするようにしています。
「今のままだと届かない。
でも、あと、この問題集のこの単元を仕上げれば、合格が見えてくる。」
こう言えるために、私は日々、各科目の配点・出題傾向まで把握するよう努めています。
塾生が志望する大学の赤本も最新版ではなく、10年、15年遡って傾向を探ります。
もちろん、そうやっても塾生が受験する年に傾向が変わることもある。
それでも「今やるべきこと」を具体的に伝えられる先生でありたい。
耳ざわりのいい言葉より、道筋を示す言葉の方が、生徒を救うと信じています。
③ 「知らない」を放置しない
教育現場に長くいると、「慣れ」が怖くなります。
制度も入試方式も、年ごとに変わる。
でも忙しい中で「まあ今年も同じだろう」と思い込んでしまうことがある。
それが一番危険です。
結果的に、それが生徒の進路を狂わせてしまうこともある。
例えば、最近こんなことがありました。
ある塾生の農学部志望の友達が「合格可能性が少しでも高い国立大だから」と、
先生に勧められて佐賀大学の農学部に志望を変更したそうです。
そして、その子は唯一得意な科目である化学を春からこの秋までずっと勉強していたそうです。
学校の先生が佐賀大農学部を薦める際に「化学を頑張れば行ける可能性がある」と言ったから。
私はその話を聞いて、ふと違和感を覚えました。
佐賀大学の理工学部・後期なら、確かに理科一教科(化学)で勝負できます。
しかし、農学部は前期が数学と英語、後期は数学1教科。
化学をやっても共通テストでしか使わない。
調べてみると、やはり私の記憶どおりでした。
志望が佐賀大の理工学部ならまだしも、農学部では戦略がまるで違う。
おそらく“佐賀大の理系=理科で受けられる”という慣れが、
誤った指導を生んでしまったのだと思います。
私はたまたま覚えていたから気づけましたが、
本来は志望校決定時に受験科目と出題傾向を一つひとつ確認すべきです。
それを怠ると、生徒の一年を狂わせかねません。
「知らないまま言い切る先生」にだけは、絶対になりたくない。
もちろん受験生本人や保護者もです。
「自分の未来や可能性を他人の手に委ねてはいけない」と塾でも口を酸っぱくして言っています。
自分の未来は自分で責任を取って、自ら情報収集をしなくてはいけません。
④ 否定を恐れず、仮説を立てて話す
先生だって人間です。
「先生、それ違います」と言われると、少し傷つきます。
でも、そこで無難なことしか言わなくなってしまったら、
もう“対話”ではなく“報告”になってしまう。
私は、あえて仮説を立てて話すようにしています。
「君ってこういうタイプじゃない?」「だったら、こういう勉強法が合うかも」
――こういう仮の提案を出すことで、
生徒が「いや、実はそうじゃなくて」と本音を話してくれることがある。
間違ってもいいんです。
一度“間違っても踏み込む覚悟”を持つことが必要なんです。
そこからしか、本当の理解や信頼は生まれないと思います。
ただ「ごめん勘違いしてた」とか「ごめん、そうだったんだ。そういうつもりだったんだ」
と「ごめんなさい」する必要があります。
自分は生徒ではない。普段の言動だけでは察しきれない、勘違いや思い違いは必ずあるのです。
ただし、踏み込むことで得られる信頼関係や人間関係もあると思っています。
⑤ 方針変更を嫌がらない
受験期には「志望校を変えたい」「科目を変えたい」などの相談がよくあります。
正直、手間がかかります。学校だったら合格に必要な単位の計算などもあり、塾よりも大変でしょう。
塾でも、教材の変更、スケジュールの組み直し、教室の確保……。
でも、私はそれを嫌がらないようにしています。
なぜなら、方針を変えたいというのは、
子どもが自分の将来を真剣に考えた証拠だからです。
迷いは成長の途中にあるもの。
それを「今さら変えるな」と押さえつけるのは簡単ですが、
「どうすれば間に合うか」を一緒に考える方が、ずっと大切です。
私はこれまでにも、12月や1月に志望校を変えた生徒を何人も見てきました。
間に合うかギリギリの戦いでも、最後まで食らいついて合格した子はいます。
その姿を見るたびに、
「方向転換は迷いではなく、意思の表れだ」と思います。
おわりに
ここまで書いた5つのことは、どれも特別なことではありません。
でも、忙しさや慣れの中で、意外と忘れてしまいがちな姿勢ばかりです。
学校の先生方も塾の先生方も多くは誠実で熱心です。
けれど、制度や会社の“正しさ”を守るあまり、個の想いを聞く余裕が奪われることもある。
私たち塾は、その制度の外にいる者として、もう一度「個の声」を拾い上げる役割を担うべきだと感じています。
「先生が正しい」ではなく、「その子の選択が、より良い実りを得られるように」――
それを支えるのが、塾という場所の存在意義だと思っています。
教育は、先生の都合ではなく、生徒の時間の上に成り立つ。
そのことを、いつも忘れないようにしたい。
子どもたちの“今”は、待ってくれません。
だからこそ、私たち支える側、教える側が迷っている“今”こそが、
子どもたちにとって、最も重たいハンディキャップになるのかもしれません。
その重みを胸に、今日も私は机に向かっています。







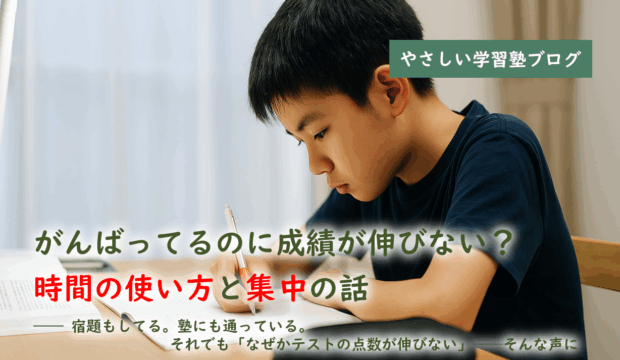
コメント