部活を引退したあと、
多くの子がこう言います。
「時間がたくさんできたから、これから勉強を頑張ります」と。
その言葉を聞くと、親も少し安心します。
「これでようやく本気を出してくれるかもしれない」と。
でも実際は――
時間が増えた子ほど、勉強が進まない。
その理由は、単純です。
「時間」を目標にしてしまうからです。
私はいつも塾でこう話します。
勉強は“時間”ではなく、“量”です。
「今日は3時間勉強した」
という言葉に、あまり意味はありません。
3時間かけても、単語を10個しか覚えていなければ、
1時間で30個覚えた子に勝てない。
勉強の成果を決めるのは、どれだけ進んだかであって、
どれだけ時間を使ったかではないのです。
長い時間を確保して勉強しようとすると、
多くの子が“ダラダラ勉強”に陥ります。
それは「パーキンソンの法則」という心理の罠です。
――人は、与えられた時間をいっぱいに使うように行動してしまう。
つまり、3時間の枠を決めた瞬間、
その3時間の中に作業を“引き延ばしてしまう”のです。
集中は途切れ、
ペースは緩み、
「やっている気分」だけが残る。
本当に強い学びは、時間ではなく“密度”で動きます。
3時間かけてやる内容を、1時間でやり切る。
その緊張感の中でこそ、理解力と集中力は鍛えられるのです。
だから、私はあえて言います。
「3時間勉強する」と決めるより、
「30問解く」「50語覚える」「1章読んでまとめる」――
そうした“量”を基準にした目標を立てなさいと。
時間は、その結果に“あとから付いてくる”ものです。
1時間で終わればそれでいい。
もし30分で終われば、もっといい。
そうやって、時間を“短く圧縮していく”ことが、
本当の意味での成長です。
この考え方は、部活にも似ています。
練習時間を長くすることが目的ではなく、
その中で“どれだけ質の高い動きができたか”が大切ですよね。
ダラダラ3時間練習するよりも、
集中して1時間取り組む方が上達は早い。
それと同じです。
「勉強を長くする子」ではなく、
「勉強を濃くする子」になる。
その違いが、半年後には決定的な差になります。
そして、もうひとつ大事なこと。
「量」を目標にすると、達成感が明確に残ります。
「今日は20問解けた」「昨日より5語多く覚えた」――
それは、成果が目に見える喜びです。
時間を目標にしていると、「3時間やったのに覚えてない」で終わる。
量を目標にすれば、「これだけ進んだ」で終われる。
その違いが、勉強を“苦行”から“積み重ね”に変えるのです。
もし、あなたのお子さんが今、
「時間はあるのに進まない」と感じているなら、
それはサボっているのではありません。
勉強の測り方が間違っているだけです。
時間という“空気のようなもの”を測るのではなく、
「できた」「覚えた」「解けた」という“形”を測る。
それだけで、学びの景色は一変します。
焦って時間を増やすのではなく、
内容を濃くする。
その一歩を踏み出した子は、
やがて時間すら忘れて、夢中で学び始めます。
そのとき初めて、“時間の壁”は静かに崩れていくのです。
次回・第4回 第3パートでは、
「リズムを失った日々を取り戻すには」
というテーマで、
“量を軸にした習慣づくり”の具体的な方法をお話しします。






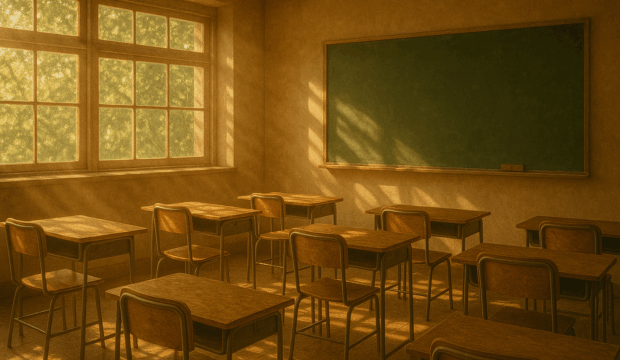
コメント