――「わからない」をどう受け止めるかで、すべてが変わる。――
1.「教えたはずなのに、覚えていない」
塾でも家庭でも、こんな声をよく聞きます。
「何度も教えたのに、次の日には忘れてるんです」
「ノートを見ても、どうやって勉強していいか分かってないみたいで……」
親としては当然、戸惑います。
「どうしたら覚えられるの?」「どうやって教えたらいいの?」
と、つい『教え方』を探し始める。
でも、ここに大きな落とし穴があります。
それは――『勉強の仕方』を教えることと、『学び方を育てること』は違うということ。
2.「わからない」は、怠けではない
「勉強の仕方がわからない」という言葉には、
いくつかの意味が隠れています。
どう始めたらいいのか分からない
何を優先すればいいか分からない
努力しても成果が出ず、自信を失っている
つまり、『やる気がない』のではなく、構造が見えていないんです。
学ぶとは、本来「やり方を見つけるプロセス」そのもの。
最初からできる子なんて、ひとりもいません。
親が「なぜ分からないの?」と焦るほど、
子どもは「もう自分はダメなんだ」と思い込みやすい。
『わからない』は、怠けではなく、成長の入口なんです。
3.「教える」と「寄り添う」は別の行為
親が子に勉強を教えるとき、
いつのまにか「説明する=理解させる」と思いがちです。
でも実際には、理解とは『聞いた瞬間に生まれる』ものではなく、
『考える余白』の中で育ちます。
たとえば、
「これが答えだよ」と言う代わりに、
「ここまでは分かってるね。次はどう思う?」
と一呼吸置くだけで、子どもは考え始めます。
親の言葉が減るほど、子どもの思考は増える。
『説明』よりも『余白』。
それが、理解を深める関わり方なんです。
4.「勉強の仕方」を言葉で説明できる子は少ない
中学生でも、「どうやって勉強してるの?」と聞くと、
多くの子がこう答えます。
「えっと……とりあえずノート見てます」
つまり、手順を自覚していない。
「やり方」は、本人の中でまだ無意識の感覚なんです。
だから、まずは『やり方を言葉にする』手伝いをしてあげてください。
「今日は何から始めたの?」
「どこが分からなかった?」
「明日はどこをやってみようか?」
この3つの質問で、
子どもは自分の勉強を『構造として見る』練習ができます。
それが「勉強の仕方を身につける」第一歩です。
5.『できない』のではなく、『自分のやり方を知らない』だけ
勉強が苦手な子ほど、「できない」と思い込んでいます。
でも実際は、自分のやり方をまだ見つけていないだけ。
たとえば、
・読むのが得意な子は「視覚型」
・話すのが得意な子は「聴覚型」
・手を動かして覚えるのが得意な子は「体感型」
勉強の仕方は、性格や感覚で変わる。
にもかかわらず、『一つのやり方』を押しつけられると、
「自分はダメだ」と感じてしまう。
大切なのは、「合ってない方法を責めない」こと。
学びの形は、十人十色でいいんです。
――『できない』を、少しずつ『分かってきた』に変える関わり方。――
6.「やり方がわからない」を『観察』する
子どもが「勉強の仕方がわからない」と言うと、
多くの親御さんは、すぐにアドバイスを始めます。
「こうすればいい」「ああすればいい」と。
でもまずは、『観察』から始めてください。
ノートの取り方、問題の解き方、机の座り方。
一緒に見てみると、意外な発見があるはずです。
・ノートを取ることに時間を使いすぎている
・正解を写すだけで、自分の言葉で整理していない
・わからない問題で手が止まったままになっている
これらは「能力不足」ではなく、習慣設計の未完成なんです。
最初にすべきは「助ける」より「観る」。
そこから、必要な支援が見えてきます。
7.『自分で見つける力』を育てる3つのステップ
塾で私がよく使うのが、この3ステップです。
親子でも取り入れられる方法なので、参考にしてください。
ステップ① 気づきを『言葉』にする
まずは、「何がわからないのか」を言葉にする練習。
「英語が苦手」→「単語の意味がすぐ出てこない」
「数学が難しい」→「途中式がごちゃごちゃする」
抽象的な悩みを具体化すると、
次に『何をすればいいか』が見えてきます。
この『分解力』こそ、勉強の本質です。
ステップ② 方法を『試す』
次に、「やり方」を決めすぎず、小さく試す。
ノートを縦に半分使ってまとめてみる
読むだけでなく、声に出して覚えてみる
1日10分だけ、昨日の復習をしてみる
試すこと自体が「勉強の練習」。
上手くいかなくても、それは『失敗』ではなく『データ』です。
ステップ③ 結果を『共有する』
試した後は、必ず誰かに話してみましょう。
親でも、先生でも、友達でも構いません。
「昨日の方法、少しやりやすかった」
「これ、あんまり覚えられなかった」
この「言葉にして共有する」行為が、
学びを『自己管理』に変えていきます。
8.塾で起きた、小さな変化の話
ある中学2年生の女の子がいました。
勉強は嫌いではないのに、成績が安定しない。
理由を聞くと、「勉強の仕方が分からない」と。
私はこう提案しました。
「じゃあ、今のやり方を『先生に教えて』みて」
彼女は最初、うまく言葉にできませんでした。
でも、少しずつ説明していくうちに気づいたんです。
「私、問題を読んでから考えてないかも」
その瞬間、顔が変わりました。
『自分の弱点』を自分で見つけたんです。
それから数週間後、彼女のノートは整理され、
点数も上がり始めました。
でも、いちばん大きな変化は――
「勉強してると、ちょっと楽しいかも」という言葉でした。
子どもは『やり方』を教えられて変わるのではなく、
自分で発見した瞬間に変わるんです。
9.親ができる3つのサポート
① 見守る時間を『区切る』
ずっと見ていると、子どもは「監視」と感じます。
だから、15分だけ一緒に見る、それで十分です。
「最初の15分」だけでも、安心感が生まれます。
② 『できたこと』を言葉にする
結果ではなく、行動を褒める。
「ちゃんと始めたね」
「続けようとする姿勢がいいね」
これだけで、子どもの脳は『やる気スイッチ』を入れやすくなります。
③ 『わからない』を責めない
「まだわからない」には、『もう少し伸びる』という希望が含まれています。
焦らずに、「そっか、今はここまでね」と受け止めてください。
安心して『わからない』と言える空気こそ、学びの土台です。
🌿 全体のまとめ
「勉強の仕方がわからない」は、怠けではなく設計の未完成。
教えるよりも、観察・言語化・共有が重要。
子ども自身が『自分のやり方』を見つけるとき、学びが自分事になる。
親は『わからない』を受け止める安全基地。
勉強とは、知識を増やすことではなく、
「どうやって自分を動かすか」を学ぶ時間でもあります。
子どもが自分のやり方を見つける瞬間――
それは、親にとっても『信じて待てた自分』を発見する瞬間なんです。
🎬 次回予告
「反抗期で親の言うことを聞かない」
ぶつかることは、離れていることではない。
反抗は、成長の証――。
次回は、親子の『言葉の距離』をどう整えるかをお話しします。







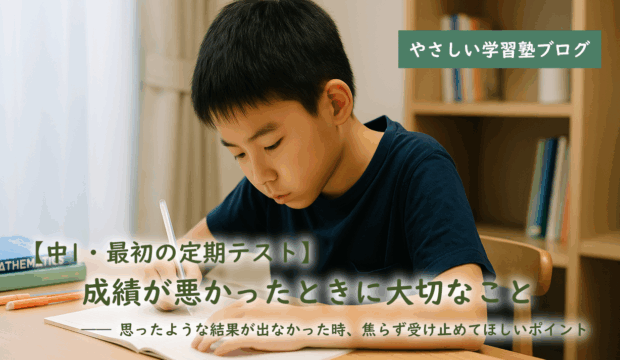
コメント