前回は、勉強を“持久走”にたとえて、
「追いつこうとしても、前はもっと先へ進んでいく」というお話をしました。
今回は、その持久走で唯一、誰かが隣を走ってくれる時間――
つまり“授業”の価値について考えてみましょう。
子どもたちにとって、授業とはただの時間ではありません。
先生が伴走しながら、ペースを整えてくれる貴重な区間です。
その1時間は、知識を教わるだけの時間ではなく、
理解の方向を修正してもらえる瞬間でもあります。
「ここでつまずきやすい」「ここは飛ばしていい」「この考え方を使うと楽になる」
そうした“勉強の考え方”を、先生は目の前で見せてくれています。
それを一緒に体験できる時間は、思っているよりずっと短い。
けれど、その一時間を“参加しない”まま過ごすと、どうなるでしょうか。
たった一回、たった一時間でも、
それは単なる「出席していない」という意味ではなく、
その単元の“走り方”を知らないまま走り続けるということになります。
私たちが勉強を教える立場で感じるのは、
「わからない」と言っている子どもたちの多くが、
実は“授業にいなかった”か、“心がそこになかった”という共通点を持っていることです。
身体は教室にいても、心が授業に参加していなければ、
理解の流れからは置いていかれます。
たとえば、黒板を写すことに集中しすぎて、
先生の声を聞き逃してしまう。
ノートは綺麗なのに、内容が頭に入っていない。
それもまた、「授業に参加していなかった」ということなのです。
そして、その“いなかった一時間”を取り戻すのは想像以上に大変です。
なぜなら、授業というものは、一方通行ではなく流れの中で成立しているからです。
ひとつ前の説明があって、次の話が理解できる。
ひとつの疑問があって、次の発見がある。
その流れの途中を切り取っても、意味は繋がりません。
私はよく、「授業を一回逃すと、三回分の復習が必要になる」と言います。
その一時間の中に含まれている“前提”や“伏線”を、
あとから自分で拾い集めるのには、それだけの時間がかかるからです。
そして、その間に本人の“自信”が失われる。
「なんで自分だけわからないんだろう」「やっても追いつけない」――
そう感じるようになった瞬間、
子どもは勉強そのものよりも“置いていかれる不安”に心を奪われてしまうのです。
授業とは、単なる知識を伝える場ではありません。
先生が「ここが大事だよ」と声をかけ、
友だちが「そういうことか」と顔を上げる。
その一連の空気を、子どもは肌で感じながら、
“理解するという営み”を体験しているのです。
その空気の中に“参加していない”ということは、
勉強の内容だけでなく、学びそのものの“体験”を失うということでもあります。
塾で私たちが行うのは、
その「失われた体験」を取り戻す仕事です。
ノートを開き、説明を繰り返し、
もう一度、学びの空気を感じてもらう。
でも、それは本来――失う前に守るほうがずっと易しいのです。
授業に「いる」ことは、
ただ席に座って「いる」という意味ではありません。
その時間の中で、“理解の呼吸”を感じているかどうか。
たったそれだけの違いが、のちに何倍もの差になる。
それが、勉強という時間の厳しさであり、
そして、学びの世界の静かな真実なのです。
次回は、このシリーズ第1回の締めくくりとして――
「早く始めることは焦りではなく、予防である」
というテーマで、“親の行動のタイミング”についてお話しします。




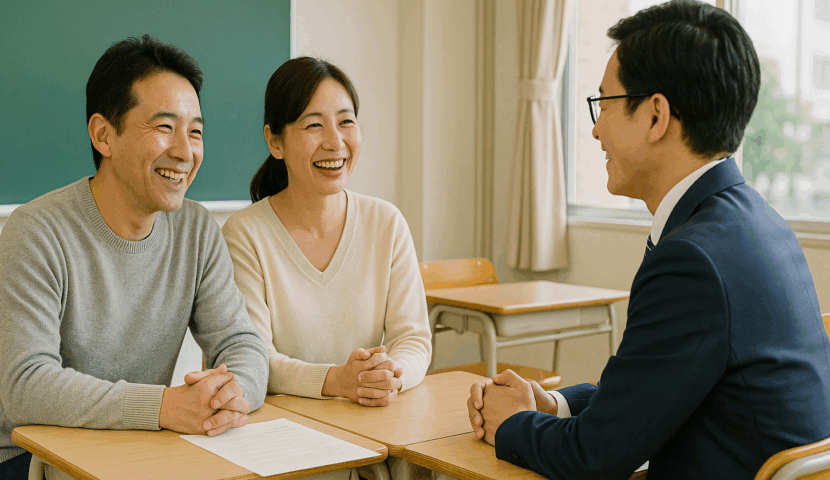
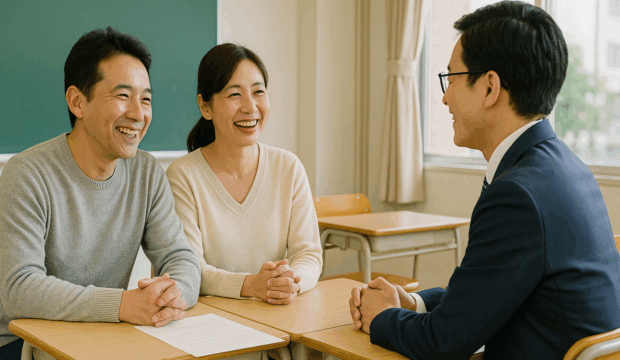
コメント