宿題もしてる。塾にも通っている。それでも「なぜかテストの点数が伸びない」──そんな声に、やさしい学習塾からお応えします。今回は、「勉強時間の使い方」と「集中」という視点から、成績が伸びる第一歩を考えていきましょう。
1) 1日1時間の勉強。その時間、本当に使えていますか?
たとえば、宿題とは別に「毎日1時間、家庭学習している」という中学生がいるとします。それ自体は素晴らしいことです。
しかし、その1時間を5教科に均等に配分していたとしたらどうでしょうか?
1教科あたり、たった12分です。
2) 集中する前に終わる“12分間学習”の落とし穴
人が学習などに集中するには、10分程度の助走時間が必要だそうです。また、作業が中断された後に再び集中状態に入るまでには、簡単な作業でも約8分、複雑な作業では最大25分かかるという研究結果もあります(Gloria Mark/カリフォルニア大学アーバイン校)。
つまり、1教科12分の勉強では「ようやく集中しかけたところで終わる」ことになります。
これを30日間続けたとすると、どの教科も集中していない学習時間が合計で6時間になる可能性があります。
3) 教科を絞れば、学習の質が変わります
同じ1時間の勉強でも、2教科に絞って使うだけで効果は大きく変わります。
1日30分×2教科で集中学習が可能に
- 英語:30分
- 数学:30分
この配分を1ヶ月続ければ、1教科あたり15時間の勉強時間。3分の1でも集中できていれば、1つの教科に5時間の集中した学習時間が確保できる計算です。
英語や数学は授業頻度が高く、復習の成果が成績に反映されやすい教科です。まずは「平均点に追いつくこと」を目指しましょう。
4) 勉強は1日1時間まで。あえて「制限」をかける理由
やさしい学習塾では、家庭学習は1日1時間までという制限を設けることを推奨しています(宿題を除く)。
「それ以上やってはいけない」と制限されると、子どもは「それなら、もう少しやってみようかな」と感じやすくなります。何かを禁止・制限されると、かえってその行為や情報に対する関心や欲求が高まるという心理現象です。これをカリギュラ効果と言います。
学ばない時間も、学びの一部です
子どもたちには、勉強する時間とは別に、
その前でも後でもなく、ただ“何をするか決まっていない時間”があります。
この時間をどう使うかは、本当はとても大切なことです。
でも、それは「有意義に使わなければならない」という意味ではありません。
たとえば、こんな過ごし方も——
- 外に出て少し体を動かす
- ソファに転がってぼーっとする
- 漫画を読む、本を眺める
そんなふうに過ごす時間も、ちゃんと意味のある時間です。
勉強で得た知識や気づきは、すぐに結果として現れるものではありません。
覚えたこと・考えたこと・わかったことを、心の中で“なじませる時間”が必要なのです。
それが、勉強していないように見える「余白」の時間。
でも実は、学びを深めるために欠かせない一部でもあるのです。
「読む」力の入口は、漫画でもいい
たとえば、漫画を読むという行為。
一見、娯楽のように見えても——
- 文字を目で追う
- 物語の展開を理解する
- 登場人物の心を想像する
それらはすべて、立派な「読む力の訓練」です。
最初から活字を無理に読ませなくても大丈夫。
「面白い」と思える読書体験の入口が、いつか自然に本の世界へとつながっていきます。
やさしい学習塾では、学びの時間も、その外側の時間も、どちらも等しく大切なものとして捉えています。
5) 「もっとやりなさい」は逆効果になることも
子どもが自分から勉強を増やすのは歓迎すべき兆候です。
ただし、保護者から「もっとやりなさい」と言ってしまうと、逆にやる気を失うことがあります。
“やらされる勉強”は続かず、“自分でやろうとした勉強”が伸びます。
6) 音読・単語・すらら復習は、勉強時間にカウントしなくてOK
以下の学習は、気軽に日常へ組み込める内容であり、勉強時間の枠に入れなくて大丈夫です。
- 英単語や漢字の暗記(5〜10分)
- 教科書の音読
- すらら等を使った小学校内容の復習
7) 夜のルーティン:「今日を振り返る時間」は、心の成長に直結します
眠る前に、1日を順番に思い出す時間を5分だけつくってください。特別な出来事がなくてもかまいません。
「朝起きて、学校へ行って、給食であんな話をして、授業ではこんなことがあって、
帰り道にこんなことがあって、夜ご飯はこれで……宿題をして、本を読んで、今寝てる」
これを習慣にすることで、子どもは“1日を生ききった”という実感を得られます。
良かった日も、悪かった日も、何もなかった日も関係ありません。
たった5分の振り返りで、子どもは“今日という日をちゃんと生きた”という実感を得られます。
「今日ボクはいっぱい頑張った。1日過ごせた。明日も頑張ろう。」
この感覚こそが、自分を信じ、明日を生きる力を育てる原点です。
8) まとめ:今は“習慣と集中”を整える時期です
- 1日1時間でも、分散しすぎると「集中できていない学習時間」になります
- 教科を絞れば、「集中できた時間」が積み上がります
ここでお伝えしたいのは、「量より質」ではなく、「量を支える“集中と習慣”をまず整える」という視点です。
勉強が得意になれば、いずれ学習量は自然と増えていきます。
ですが、最初からすべてを求めるのは現実的ではありません。
まず身につけるべき2つの土台
- 「毎日机に向かう」という習慣
- 「時間内に集中して終える」という体験
制限があるからこそ、取り組みやすくなる。
自分で動く子は伸びる。外から押されると、止まる。
「がんばり方を整える」ことが、最初に必要な支援です。
やさしい学習塾では、“無理をさせずに、力をつける”学習習慣を重視しています。
参考:Gloria Mark, “Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity” (Hanover Square Press, 2023).




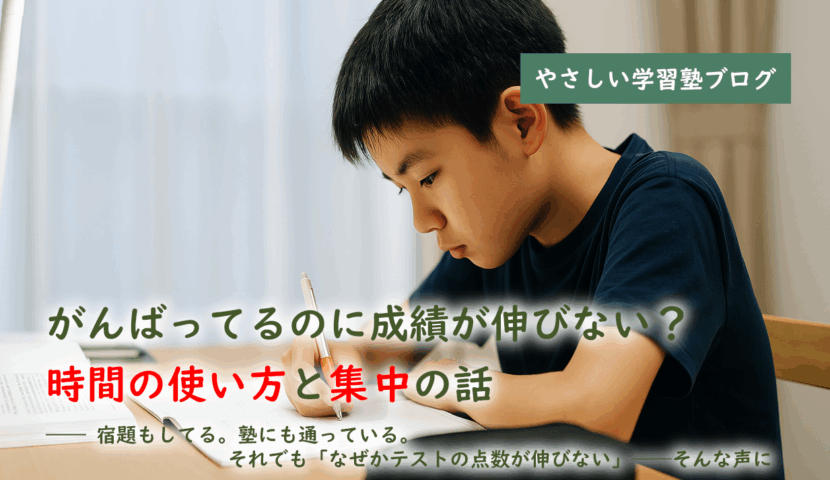



コメント